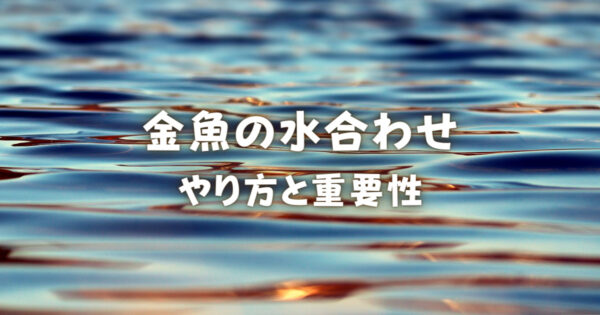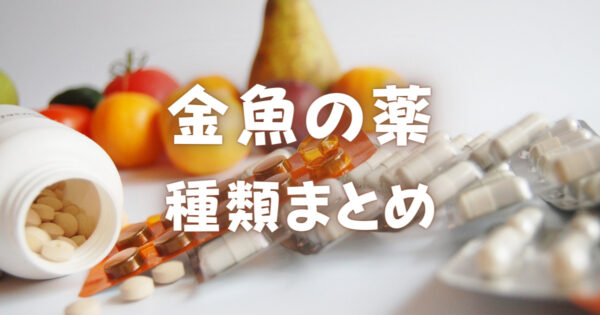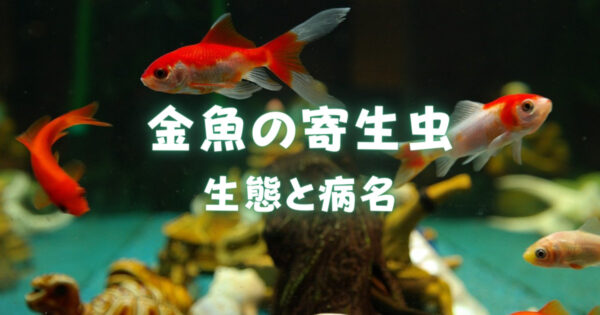金魚の薬浴の方法とやり方、注意点について、初心者の方にもわかりやすく紹介しています。
金魚の病気を治療していると避けられない金魚の薬浴。
金魚病気の治療には専用の薬が存在し、適切な方法で薬浴を行う必要があります。
もちろん、金魚が病気にならなければ薬浴を行う必要もありません。
ですが、どんなにベテランの飼育者でも病気になるときはなるのが金魚飼育の難しいところ。
どれほどしっかり、適切な治療をしていても、金魚も人と同様に病気になります。
病気になった際、いかに早く気付き適切な治療を行えるかが重要です。
今回は、薬浴を行う上での基本的なやり方をまとめています。
大切な金魚が病気になって、初めて薬浴に挑戦する方や、これまで薬浴に成功したことがないあなたにとって、最適な情報をお届けします。
普段の金魚飼育の薬浴にもぜひ、積極的に取り入れてください。
この記事では、記事内の写真の紹介に、インスタグラムの投稿をピックアップし、薬浴の画像を閲覧できるようにしております。
また投稿の最後に、金魚の薬浴や塩浴に便利な濃度計算表(自動計算)へのリンクを掲載しています。
誰でも完璧な濃度で薬や塩の量の計算ができます。ぜひご利用ください。
金魚の薬浴とは
金魚の薬浴とは、その名の通り金魚を薬の入った水の中で泳がせることを指します。
沢山の種類がある金魚の病気に対して、様々な種類の薬が開発されており、それぞれ使用量と薬浴を行う期間が決まっています。
薬浴に使用する薬はどれも細菌や寄生虫の活動を止めたり、死滅させる「化学成分」です。
薬浴を行う必要がある時点で、金魚は病気や寄生虫症によってとても弱っています。
金魚にとって負担のない、適切な方法で薬浴を行わないと、ときとして薬浴は「金魚に致命的なダメージ」を与える危険もあります。
ここからは、どのような病状の金魚にも対応することができる「金魚の薬浴の基本的な方法」を丁寧に紹介しています。
金魚の薬浴の方法
金魚の薬浴の方法を順番に記載しています。
ぜひ、次回からの薬浴の参考にしてください。
薬浴用の容器には必ず金魚⇨液化した薬の順序で投入します。
薬の入れ方、量り方に関しても誰でもできる簡単な方法を紹介しています。
薬は怖いからと、自己流で薬の濃度を薄くする、もしくは濃くすることのないようにしましょう。
薄くすると効果が出ず、治療が長引き、金魚が弱ることがあります。
薬にはそれぞれ指定の薬浴期間があります。
薬効を維持し完全に回復させるために、薬浴開始から4日〜5日ほどのタイミングで一度、
新しい薬浴水を換えることが重要です。
症状の悪化が止まったことを確認し、薬浴をストップします。
多くの金魚用の薬は薬浴期間を合計7日前後に定めています。
7日経っても症状の悪化が止まらなかったり、金魚がいかにも衰弱している場合は
病気の種類と薬が合っていない可能性があります。
症状を再度確認し、原因の調査を行いましょう。
①水量10リットル以上の容器を用意する
金魚の大きさや数にもよりますが、数センチサイズの金魚で最低でも10リットル以上の容器で薬浴を行いましょう。
サイズは大きい分には問題ありませんが、小さすぎると水質の維持が難しく、水が汚れるスピードが速くなり、かえって金魚を弱らせることになりかねません。
薬浴は最低1日、最長で2週間ほど行う可能性があるため、できるだけ水量は確保できるようにしてください。
水量さえ確保できれば、容器の種類はバケツ等なんでも構いません。
②対象の金魚を隔離する
病気の種類にもよりますが、薬浴は基本的に病気になった個体を別の飼育ケースに移動させてから行います。
理由としては、薬浴の薬は非常に強力であることが挙げられます。
水槽全体で行うと、悪い細菌や寄生虫だけでなく、水中の良いバクテリアもまとめて殺してしまうからです。
病気が明らかに全体に伝染している場合や、ウオジラミなどの寄生虫が原因の場合は、やむを得ず隔離せずに、水槽全体を薬浴したり、一度リセットすることもあります。
このようなことを未然に防ぐためにも、「できるだけ病気の発生を未然に防ぐ」目的でトリートメントと呼ばれる技術が存在します。
トリートメントに関してはこちらに実践的な内容をまとめています。
注意点として、隔離を行う際は「薬がまだ入っていない普通の水の状態」で行います。
理由としては、薬を投下した水にいきなり金魚を移動すると、金魚への負担が非常に大きく、無駄な体力を消耗しかねないためです。
この時の水に関しては、「カルキを抜いた水道水」で問題ありません。
移動の際もいきなり新しい水にぽちゃんとしてしまうと、金魚がびっくりしてしまうため、袋などに一度飼育水ごと金魚を入れ、新しい水を少しずつ袋に入れる要領である程度慣らしてから移動するようにしましょう。
この水に慣らす技術を、一般的に「水合わせ」と言います。
金魚の水合わせのやり方、移動方法に関してはこちら
「容器の準備⇨新しいカルキを抜いた水を準備⇨水合わせ⇨金魚の投入⇨薬の投入」の順番が鉄則です。
③金魚の病気に対応した薬を投入する
ここまできていよいよ金魚の薬を投入します。
投入する際の注意点として、必ず「液化した薬を少量ずつ入れる」ようにしてください。
金魚の薬は粉末状のものも多く、そのまま投入すると金魚が誤って食べてしまうことが多く、極めて濃い濃度の薬が金魚の体内に吸収されてしまいます。
粉末・液体問わず、まず水で希釈し、容器の水量から適切な量をスポイトで吸い取った上で少しずつ溶かしてあげてください。
この時、薬の濃度は規定量を絶対に守ってください。
ベテランの飼育者の中には肌感で薬を投下する方も少なからず存在しますが、これは長年の経験があってこそです。
薬は薄すぎると効きません。濃すぎると金魚に大きな負担をかけます。
ですが、ほとんど全ての金魚の薬が「大規模飼育」を想定して販売されており、一般家庭サイズの水槽だと、計量が極めて困難です。
計量にはコツがあり、適切な量を計測するのも、金魚飼育のテクニックの一つです。
すぐに揃うものばかりですので、ぜひ、この機会に正しい薬の計り方・薬の作り方もマスターしてください。
金魚の薬の計り方に関してはこちら
④薬浴中に最低一度は水換えを行う
金魚の薬浴では、薬によって最適な薬浴期間が設定されています。
数日であれば問題ありませんが、薬浴の期間が4日以上経過している場合、一度、薬浴水を水換えをすることをおすすめします。
薬浴期間中は濾過フィルターは使用することができないため、とにかく水が汚れやすい状態です。
薬浴で金魚が死んでしまう原因として、薬の効果が現れる前に、薬浴水の水質悪化が弱っている金魚に更なるダメージを与えることが挙げられます。
できれば薬浴期間中に最低1回、1/2ほどの水量の新しい薬浴水と、水換えをしてあげるようにしましょう。
この作業を行うだけで、薬浴での金魚の病気の治療成功率は飛躍的に高まります。
ぜひ、試してみてください。
⑤症状の悪化が止まったら薬浴を終える
金魚の症状の回復状況をよく観察しつつ、「症状の悪化が止まっている」ようであれば、薬浴を終了しましょう。
この時、再度薬浴する必要は無く、真水での通常の水換えに切り替えて経過を観察しましょう。
症状が再発するようであれば、再度薬浴を開始します。
完全に回復するまで繰り返して行いましょう。
金魚の塩浴に関してはこちらで詳しく紹介しています。
金魚の薬浴の方法を学んだら、基本的な病気や薬の種類も学んでおきましょう。
金魚の病気の種類についてはこちらを参照ください。
薬の種類に関してはこちらにまとめています。
金魚の薬浴の戻し方
ここで、金魚の薬浴の戻し方についても紹介しておきます。
金魚の病気を適切に見分けた上で、早期に正しい方法で薬浴を実施した場合、治療が成功する確率は高くなります。
ですが多くの飼育者が、「薬浴での治療後、薬浴を戻す技術」を学んでおらず、病み上がりの金魚へ再度ダメージを与えて病気の再発を招いています。
薬浴の戻し方は、薬浴と同じくらい重要なスキルです。ぜひ、この機会にマスターしてください。
治療が完了した金魚がいる水槽の水には、薬が溶け込んでいます。
このとき、塩浴も併用している場合は薬と塩がどちらも溶け込んでいる状態です。
このまますぐに、元いた水槽に戻すと金魚は100%調子を崩します。
この段階でどれだけゆっくり丁寧に水合わせをしても、水質の違いが大きすぎるため、意味がありません。
薬浴後は、「とにかくゆっくりと元いた環境の水に戻す」ことを意識してください。
金魚の体表や動きをくまなく観察し、病気の再発がなければ、再度真水で水換えをします。
この時点で薬や塩の濃度は当初の1/4にまで薄くなっています。
まだまだ、元いた水槽に戻すのは早すぎるため、このまま2日ほど様子を見ます。
金魚を再度観察し、病気の進行が完全に止まっていることを確認し、真水ではなく「元々いた水槽の水」で水換えを行います。
あえて元々いた水槽の水で水換えを行うことで、この後元々いた水槽に戻る際の負担を大幅に減らすことが可能です。
ここまで行った上で、金魚に異常がなく、元気に動き回っているようであれば「治療完了」です。
丁寧に水合わせをした上で、元々いた水槽に戻します。
金魚の薬浴の注意点
金魚の薬浴を行う上で最低限守るべき注意点を記載しています。
せっかく準備した薬の効果も、台無しになってしまう危険がありますので、必ずこれらの注意点を守るようにしてください。
- 薬浴中はろ過器を絶対に使わない
- 薬浴中は餌をあげない
- 薬浴の前に、まずは塩浴
薬浴中はろ過器を絶対に使わない
ろ過器の役割は大きく分けて2つあります。
- フンや食べ残しなどの物理的なゴミを集め、バクテリアにより分解する
- 金魚から排泄される見えない有害なアンモニアを無害な亜硝酸に換える
これらはどちらも「バクテリア」が生きているから効果があります。
薬を投入した時点で、バクテリアは死滅してしまうため、薬浴用の施設に濾過器を入れてもあまり意味がありません。
薬浴中のフンはスポイトやネットで取るようにし、水が汚れるようであれば水換えを行い、同様の濃度での薬浴を実施してください。
金魚に適したフィルターに関しては別途、こちらの記事にまとめています。
薬浴中は餌をあげない
薬浴は、薬の種類にもよりますが1回の薬浴に対して長くて1週間ほどです。
薬浴中は、ろ過器を設置してもあまり意味がなく、エアレーションのみの対応となるため水が汚れやすいです。
金魚自身も、病気の治療に専念してもらう必要があるため、餌やりは基本的にストップです。
それまできちんとお世話をしている金魚であれば、1週間何も食べなくても何の問題もありません。
むしろ体調の悪い金魚に餌を与える方が、転覆病などの二次的な病気につながる可能性が高くなります。
金魚の薬浴のスタート=「絶食のスタート」です。
薬浴の前に、まずは塩浴
よく、金魚が病気になった=薬浴と記載されていますが、これは一般的な飼育者には難易度が高いです。
なぜなら、たくさんの種類がある金魚の病気とその薬を即座に判断するには、それなりに経験が必要だからです。
間違った薬で薬浴を行っても、金魚の病気は治らないどころか、隔離によるストレスで病気が悪化しかねません。
金魚の調子が悪いと感じたら、薬浴を行う前に、まず塩浴を行うことをおすすめします。
塩浴であれば、隔離をする必要もなければ、金魚に負担をかけることもありません。
薬浴だけで完治する病気は少ないですが、経験が浅いうちは、病気ではないものも病気だと勘違いして薬浴をしてしまい、無理なストレスから金魚を痛めてしまうこともよくあります。
病名がはっきりするまで、まずは塩浴を行って様子を見ることをおすすめします。
塩浴のやり方に関してはこちらで詳しく紹介しています。
金魚の薬浴の方法と注意点をマスターしよう
金魚の正しい薬浴の方法をマスターすることは、金魚飼育を安心して行う上で必須の試練です。
金魚も人と同じく、どんなに飼育者が丁寧に飼育を行っていても、中長期的には必ず病気になります。
いつ病気になっても対応できるよう、きちんと準備をしておくことと、金魚の異変にいち早く気づき、適切な病名の判断の元、適切な治療を行うことが重要です。
金魚の病気の種類に関してはこちら
金魚の薬の種類に関してはこちら
金魚の病気が発生する確率が最も高いのが「季節の変わり目」と「新しく金魚をお迎えした直後」です。
新しくお迎えした金魚には、「病原菌の持ち込みのリスク」があります。
これはトリートメントという技術で未然に防ぐことが可能です。
金魚のトリートメントのやり方に関してはこちら
金魚の病気の中には、「細菌性のもの」と「寄生虫性のもの」が存在します。
寄生虫性の病気に関しては、治療の方法が細菌性の病気と異なります。
寄生虫性の金魚の病気に関してはこちらの記事で紹介しています。